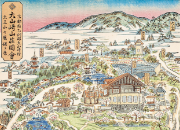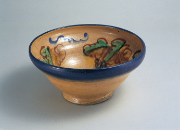スタッフブログ
掲載のお知らせ③
ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。
ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!
全5回の連載で、本日は第3回目です。
みうら氏が小学1年生の頃から続けてきた、スクラップについてお話しします。
―――
第3回 捨てられなくするための方法。
https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-20.html
―――
どうぞご覧ください。
(IK)
掲載のお知らせ②
ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。
ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!
全5回の連載で、本日は第2回目です。
みうら氏とシジュちゃんが、本館・山本記念展示室でお話しします。
―――
第2回 残そうと思っても、ふつうは残せない。
https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-19.html
―――
どうぞご覧ください。
*「フェザード・シジュ」ちゃんについて詳しくはこちら
https://www.1101.com/feathered_shiju/index.html
(IK)
掲載のお知らせ①
ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。
ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!
全5回の連載で、今回が第1回です。
―――
第1回 「マイ遺品」って、なんですか?
https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-18.html
―――
どうぞご覧ください。
*「フェザード・シジュ」ちゃんについて詳しくはこちら
https://www.1101.com/feathered_shiju/index.html
(IK)